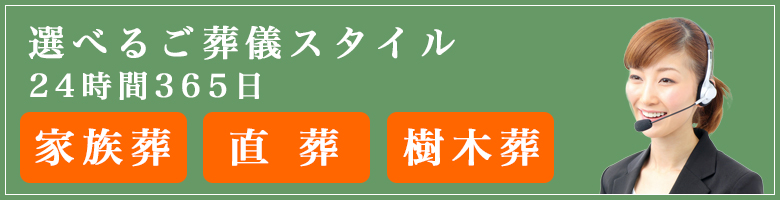焼香の知識

焼香は、通夜や葬式、また法事などでは必要な儀式となります。だからこそ、正しい焼香の方法や回数などを知っておく必要があります。周りに合わせて焼香をすれば大丈夫と考えているかもしれませんが、いざ自分が一番手に焼香をするとなると困ってしまうでしょう。焼香の知識の詳細

友人や知人などの訃報を聞いたあと、遺族の自宅などに訪問することがあると思います。 このことを弔問と言います。 いざ弔問する時に、マナーや弔問の流れなどを知らずに困惑する人も多いかもしれません。 急な弔問にも失礼なく対応できるよう、弔問についてはある程度知っておく必要があります。 そこで弔問について詳しく解説していきます。
弔問とは、訃報が届いた後、遺族にお悔やみを述べることです。 突然の訃報で動転してしまっていても、遺族への配慮を忘れずに失礼のないようにしなくてはいけません。 あくまでも遺族にお悔やみを伝え、故人へ線香をあげることが目的となるのです。
弔問する際に注意するべきことは、弔問のタイミングです。 訃報を聞いたらなるべく早く駆け付けますが、親族や故人と親しかった友人を除いては、通夜や葬式に参列します。 通夜や葬式に参列できない時に、自宅訪問を行います。 この場合は、遺族が弔問客を迎える準備があるので事前に連絡を行いましょう。 葬儀の直後は遺族の負担になってしまうので、遺族が少し落ち着いた頃である葬儀後数日~四十九日頃までがいいでしょう。
弔問時には、服装や挨拶などマナーを守っていく必要性があります。 訃報の知らせを電話などで連絡を聞いた際には、死去について色々と尋ねず、遺族の気持ちを思いやってお悔やみの言葉を伝えます。 また弔問へ行く日時等を伝え、遺族の負担を減らします。
弔問へ行く際の服装は、喪服ではなく平服で構いません。 あまりにもカジュアルな服装や、派手過ぎる服装でなければ問題はありません。 男性であればスーツや軽いジャケットを羽織るようなスーツ、女性であればワンピースやアンサンブルスーツが良いでしょう。
弔問へ行くときは、通夜や葬儀に参列しない場合には香典を用意します。 葬儀後に弔問する場合、香典には四十九日前であれば「御霊前」、四十九日後は「御仏前」と記入します。 また、手土産は必要ないものの、故人の供養のための供物を持参するといいでしょう。 花やお菓子、故人が生前好きだったものなどです。
弔問へ訪れた際の遺族への挨拶は、簡単で丁寧な言葉が良いでしょう。 「この度はご愁傷さまです。」「ご冥福をお祈りいたします。」など、弔意を表す言葉です。 亡くなった死因や経緯などを詳しく聞くようなことは避けて、遺族を気遣うことが大切です。
弔問の流れを知っておくと、スムーズに失礼なことなく弔問できます。 葬儀前と葬儀後では流れが少し違いますが、長居はしないようにします。
通夜や葬儀の前に弔問に行く場合、事前に弔問に伺う旨を伝えます。 挨拶をして家にあげてもらいます。 故人との対面は遺族に勧められた場合のみ行います。 その場合は、故人の枕もとで正座をし、両手をついて一礼します。 遺族が白布を外してから対面し、故人に一礼して合掌します。 その後遺族に挨拶をし、弔意や何か手伝えることがないか尋ねる程度にして帰ります。
遺族へ事前に弔問へ行く日程を伝えます。 弔意を表した挨拶をして、遺族側から招かれた場合や、家に上がるよう促された場合に家へ上がります。 位牌に線香をあげ、香典や供物を準備している場合はこの時に渡します。 この場合も長居するのではなく、手短に話をして帰るようにしましょう。
弔問に訪れた際には線香をあげますが、その時の線香のあげ方は故人の宗派に合わせることがマナーです。 しかし故人の宗派が分からない場合もあるでしょう。 その際は、普段自分が行っている線香のあげ方で構いません。
天台宗、真言宗
線香を3本立てる
臨済宗・曹洞宗
1本もしくは2本立てる
浄土宗
1本の線香を2つに折って立てる
浄土真宗
本数に決まりはないが、線香は寝かせる
仏壇の前に座り一礼した後、付いているろうそくに線香を付けます。 ろうそくに火が付いていない場合は、先にろうそくを付けます。 線香に直接火をつけてはいけません。 線香から煙が出れば、左手で仰いで火を消します。 火を消した線香を宗派の本数香炉に立て(寝かせて)、おりんを一度慣らして合掌します。 遺影に一礼し、遺族にも一礼して下がります。
宗派や地域によって違いはありますが、故人を供養するためのものであることは変わりありません。 順序や宗派が分からない場合でも、故人を供養する気持ちと遺族に配慮することを優先するようにしましょう。

焼香は、通夜や葬式、また法事などでは必要な儀式となります。だからこそ、正しい焼香の方法や回数などを知っておく必要があります。周りに合わせて焼香をすれば大丈夫と考えているかもしれませんが、いざ自分が一番手に焼香をするとなると困ってしまうでしょう。焼香の知識の詳細

友人や知人などの訃報を聞いたあと、遺族の自宅などに訪問することがあると思います。このことを弔問と言います。いざ弔問する時に、マナーや弔問の流れなどを知らずに困惑する人も多いかもしれません。急な弔問にも失礼なく対応できるよう、弔問についてはある程度知っておく必要があります。弔問のタイミングの詳細
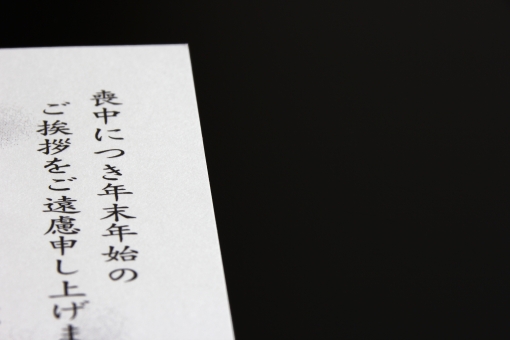
家族や親族が無くなった時に、喪に服すために喪中はがきを出します。この喪中はがきを準備する際に、送る相手や送る時期など悩む人も多いはずです。喪中はがきの書き方など、喪中はがきのマナーを詳しく解説していきます。喪中はがきの書き方の詳細

「葬式の日取りは友引を避けた方がいい」という言葉を耳にしたことはありませんか?火葬場も友引の日には休業していることも多くなっています。当たり前の知識として考える人多いかもしれませんが、実際に友引の意味などを知らない人も多いでしょう。なぜ通夜や葬儀を友引に避けるのか、葬儀の日程を決めるポイントなどを解説していきます。友引にを葬儀しない理由の詳細
葬儀プランのご案内

「家族葬」という新しい葬儀のスタイルが定着しつつあります。今までの葬儀と言えば、家族やその親族、さらには住居周辺の近所の人なども参列する大がかりなものが多かったのですが、それが家族など濃い近親者のみで葬儀を行う家族葬が当たり前のようになってきています。では、そもそも家族葬とはどのように段取りをして進めるものでしょうか。家族葬のポイントを交えて、その流れをご紹介します。家族葬プランの詳細

葬儀のあり方がどんどん変わっています。昔のように近所の人や会社の関係者などが多数参列するスタイルではなく、家族や濃い親族だけでゆったりと故人を送る「家族葬」などの、新しい葬儀のスタイルが生まれてきています。そんな葬儀のスタイルを覆す新たなスタイルとして、「直葬」が登場しています。最近登場した直葬のあり方や流れについて、詳しくご紹介します。直葬プランの詳細

団塊世代と呼ばれる昭和20年から昭和25年までの出生者が平均寿命に達するころ、日本国内では一番死亡者が増える頃とされています。そのため、お墓を確保することが出来ない「お墓難民」と呼ばれるような人も増えると予測されています。2018年になった今では、一般的に墓石を設置するお墓ではなく、その後の管理が簡素にできるような新たな埋葬の方法も登場するようになってきました。そんな新たな埋葬の方法として脚光を浴びている「樹木葬」について、今回はご紹介することにいたします。樹木葬プランの詳細

お墓への納骨にこだわらない、新しい供養のスタイルがどんどん登場しています。例えば、墓石の代わりに樹木をモニュメントとする樹木葬や、遺骨を炭化させてダイヤモンドを生成するダイヤモンド葬、そして今回ご紹介する「海洋葬」などがあります。お墓への納骨と比べて安価であることはもちろんですが、海が好きだった故人の意思を反映させることもできることで、最近利用者が増えています。海洋葬プランの詳細